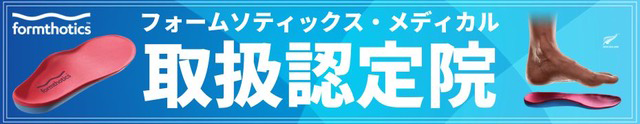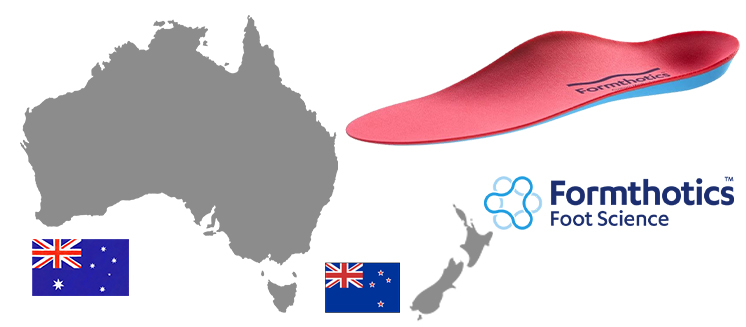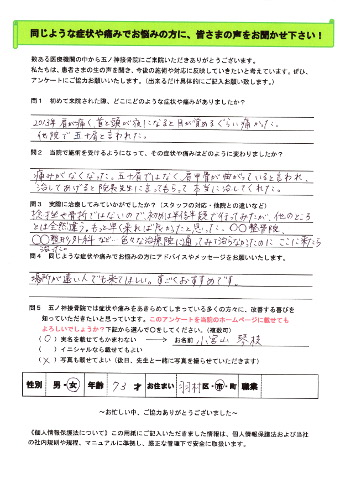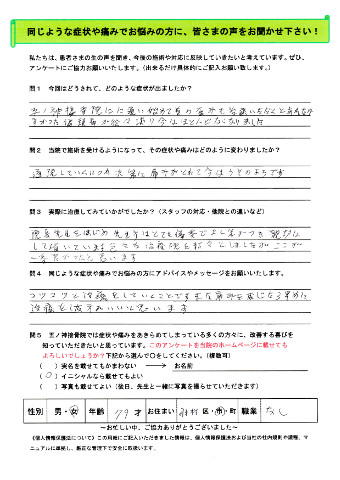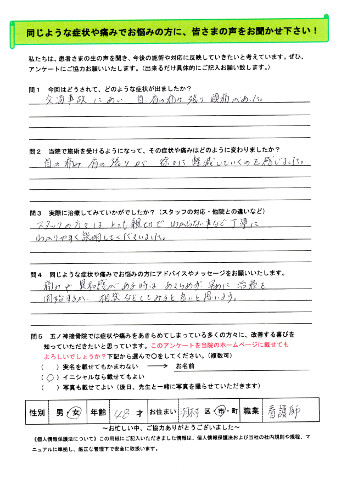首や肩まわりの筋肉は頭の重さを常に支えている状態です。首は細く体重の約1/8の重い頭を支えているので、筋肉に負荷がかかっているのです。日常生活では首が前かがみになる時間も多いです(デスクワークやスマホなど)。首や肩まわりの筋肉にはこの状態で大きな負担がかかります。負担がかかり続けた筋肉は頭痛を発生させる原因となってしまうのです。
筋肉に継続して負荷をかけると酸素不足や栄養不足になり硬化します。その状態が続けば筋肉内にしこりができます。そのしこりがやがてトリガーポイントという状態になります。トリガーポイントを発生させて筋肉は痛みの物質を出して人体が感知するのです。
頭痛に関連する筋肉(1)〜頭半棘筋(とうはんきょくきん)〜
頭痛に関連する筋肉に「頭半棘筋(とうはんきょくきん)があります。
首から後頭部に位置する筋肉で主に頭を支えるのが役割です。頭半棘筋はデスクワークなど首を前に倒す動作で使われます。疲労が蓄積し後頭部から締め付けられるような頭痛が出現します。
頭痛に関連する筋肉(2)〜僧帽筋(そうぼうきん)〜
側頭部に痛みを出す原因に「僧帽筋(そうぼうきん)」という筋肉があります。僧帽筋は後頭部から首、肩、背中にかけて位置する大きな筋肉。頭の重さを支え、腕を吊り上げています。僧帽筋が硬くなることで側頭部や顎、首などに関連痛を引き起こすとされ、片頭痛と似た症状が現れます。
頭痛に関連する筋肉(3)〜胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)〜
前述したように群発頭痛の原因はまだ解明されていませんが、目やその周囲、目の奥の痛みは「群発頭痛」と診断される場合もあります。「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」は、目の奥などから痛む頭痛と関連があります。この筋肉は鎖骨や胸骨から頭蓋骨に付いている筋肉で首を曲げたり回したりする動作(クルマの運転など)に機能します。この胸鎖乳突筋が硬くなり痛みを出すと、目の周りに痛みが現れます。

 なんと日本人の実に30%以上(15歳以上)が「頭痛持ち」であるというデータをご存知ですか。約3千万人が頭痛で悩んでいるという計算です。しかし、単なる頭痛と侮るなかれ。生活に支障をきたすほどの痛みをともなうものや病気の原因、大きな疾患のサインであることもあるのです。
なんと日本人の実に30%以上(15歳以上)が「頭痛持ち」であるというデータをご存知ですか。約3千万人が頭痛で悩んでいるという計算です。しかし、単なる頭痛と侮るなかれ。生活に支障をきたすほどの痛みをともなうものや病気の原因、大きな疾患のサインであることもあるのです。 下記に当てはまる方は是非当院にご相談ください!
下記に当てはまる方は是非当院にご相談ください!
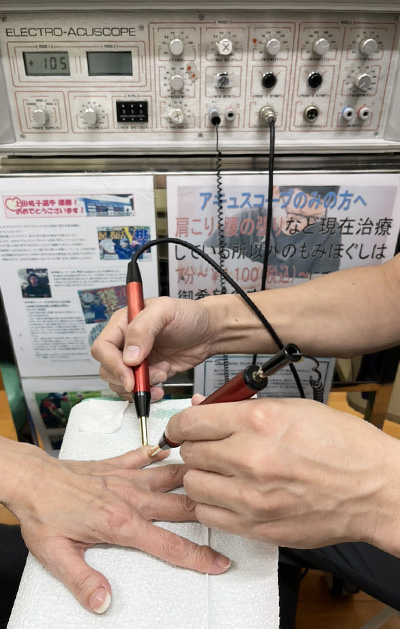
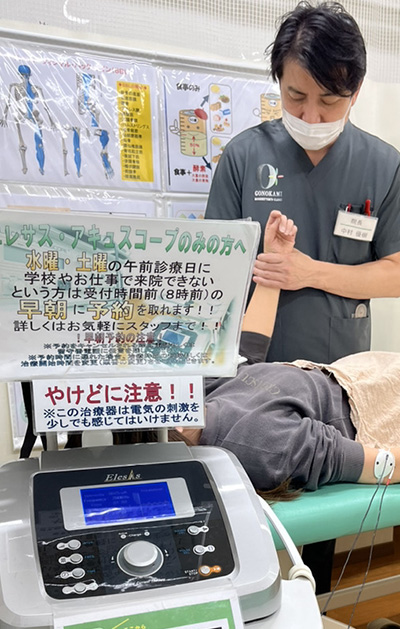

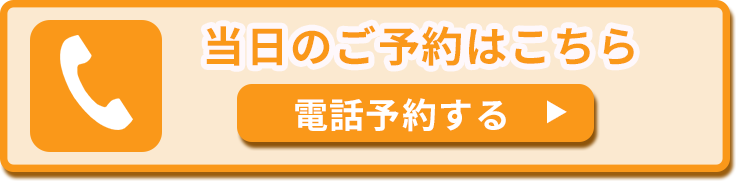


 関連痛とは痛みの原因が痛みの生じた部位と異なる部位に感じる痛みのことです。頭痛もこの関連痛にあたることが多く、原因は痛みを生じている部分ではないことがあります。当院では国家資格を持った施術者が痛みの原因を正確に把握するために、問診や検査はもちろん正確に触診して原因を突き止めます。
関連痛とは痛みの原因が痛みの生じた部位と異なる部位に感じる痛みのことです。頭痛もこの関連痛にあたることが多く、原因は痛みを生じている部分ではないことがあります。当院では国家資格を持った施術者が痛みの原因を正確に把握するために、問診や検査はもちろん正確に触診して原因を突き止めます。