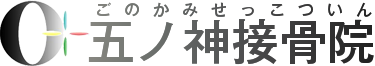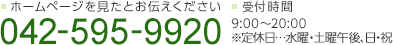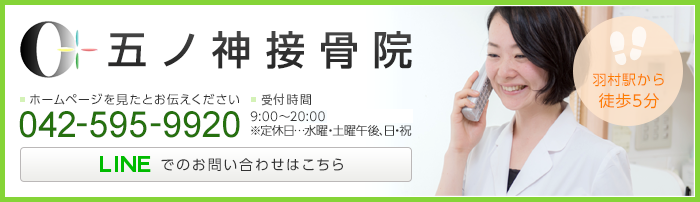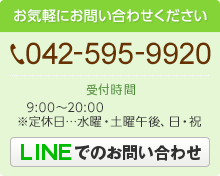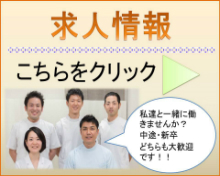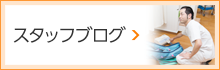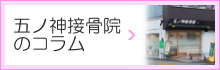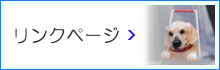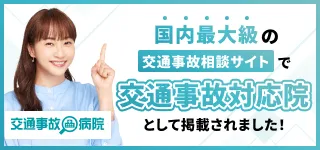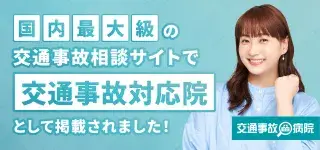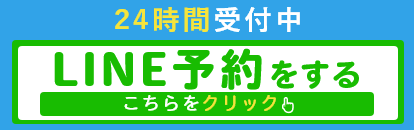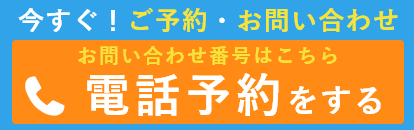特に高齢者は注意が必要!誤嚥性肺炎を防ぐためにはどうしたらいい?
2022.11.18更新
from 院長 中村 優樹
五ノ神接骨院より
高齢になるにつれて、誤嚥性肺炎になるリスクが高くなります。誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物を身体に入れる際に謝って気管が気管から肺に入ってしまい、その時に同時に入った細菌によって肺炎が起こってしまうという病気です。年齢を重ねるごとに飲み込む力が弱くなってしまい、このような症状が起きてしまうこともあるようです。そこで今日は、誤嚥性肺炎を防ぐために行っておきたいことについてご紹介していきましょう。
【誤嚥性肺炎を防ぐための方法】
1.口腔ケアを行っておく
誤嚥性肺炎が起きてしまう原因の1つに、食べ物や飲みものと一緒に口の中にある細菌が肺に入ってしまうことが挙げられます。そのため、できるだけ口の中は清潔に保っておくことが重要です。食後には必ず歯磨きを行うようにしたり、定期的に歯医者さんにいって治療を行っておくようにしましょう。そうすることによって、万が一誤飲してしまっても誤嚥性肺炎になるリスクを下げることができます。
2.しっかりと噛んでゆっくり食事をする
慌てて食事をしていると、誤って肺の方に食事が入ってしまうリスクがあります。そのため、食事の時間をゆっくりととって、しっかりと噛んで食べるようにしましょう。また、食事をとった後すぐに横になってしまうと、食べたものが気管に入ってしまう可能性もあるため、しばらくは座っておくといいでしょう。
3.のどや舌を鍛える
誤嚥性肺炎が起こってしまう要因は、飲みこむ力が弱くなってしまうことが挙げられます。そのため、誤飲を防ぐためにものどや舌を普段から鍛えておくことが重要でしょう。特別なトレー二ングを行わなくても、会話をしたり歌うことによって、自然と鍛えられます。
いかがでしたか?誤嚥性肺炎は高齢者に多い病気ですが、若い方もならないとは限りません。普段からゆっくりと食事をしたり、普段から歌ったり会話をしたりと楽しみながら、病気のリスクを下げましょう。
投稿者: